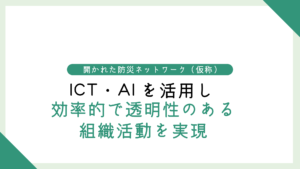なぜ私たちは「インカインド支援」を選んだのか?

こんにちは、森本たかしです。
「防災士のネットワークはボランティア精神で支えられている」とよく言われます。
でも、現実にはその“ボランティア”が正当に評価されることは、ほとんどありませんでした。
特に、私が所属していた日本防災士会では、その傾向が顕著でした。
「講演する人」だけが評価される世界
イベントがあると、表に出るのは講演を担当する一部のメンバー。
その裏で、誰がイベントを企画したのか?
誰が会場を押さえたのか?
誰が座席を並べ、マイクを準備したのか?
誰がホームページを作って集客したのか?
こうした“見えない貢献”は一切カウントされないのが当たり前でした。
おまけに講演を担当するのも、中心メンバーの中で“持ち回り”。
中堅メンバーですら、任せてもらえる機会がないまま。
そして当然ながら、講演のための学習の場も提供されません。
「人が育たない」のではなく、「育てる気がない」
組織の中で何度も聞いた言葉があります。
- 「最近の人は手伝わない」
- 「言われたことしかしない」
- 「やる気が感じられない」
でも本当にそうでしょうか?
私には、手伝っても評価されない、存在を認められない空気が、会員のやる気を奪っているようにしか見えませんでした。
そしてその結果、呆れた会員が黙って離れていく。
それを繰り返しているのが、かつての防災士会の姿でした。
だから、私たちは変えることにしました
私たちのネットワークでは、目に見える活動だけでなく、裏方の仕事も「インカインド支援=貢献」としてきちんと評価します。
- チラシを作った人
- 会場を押さえた人
- 記録をまとめた人
- SNSでイベントを広報した人
こうした活動がなければ、どんな立派な講演も成り立ちません。
だからこそ、それらもすべて「価値ある寄付」として正式に記録し、みんなで感謝し、平等に扱う。
そして、希望する人には講演の機会も学ぶ場も提供する。
学びたい人が育てられない組織に、未来はありません。
「お金ではなく、行動が価値になる」組織へ
私たちは、従来のように「上から役割を与えられる」のではなく、
「自分から貢献できる」仕組みを大切にしています。
金銭的な寄付ができなくても、時間や労力、スキルやアイデアを寄付することで、十分に組織を支えることができる。
そんな「新しい貢献のかたち」が、インカインド支援なのです。
この考え方こそ、これからの防災士ネットワークを持続可能なものにしていく鍵だと、私は確信しています。
を活用した柔軟で持続可能な運営をしたい-300x169.png)