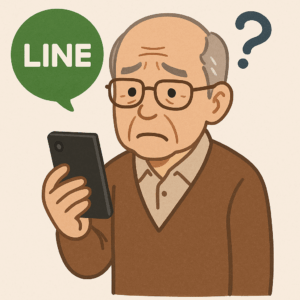🚨 その避難訓練、本当に役に立ちますか?
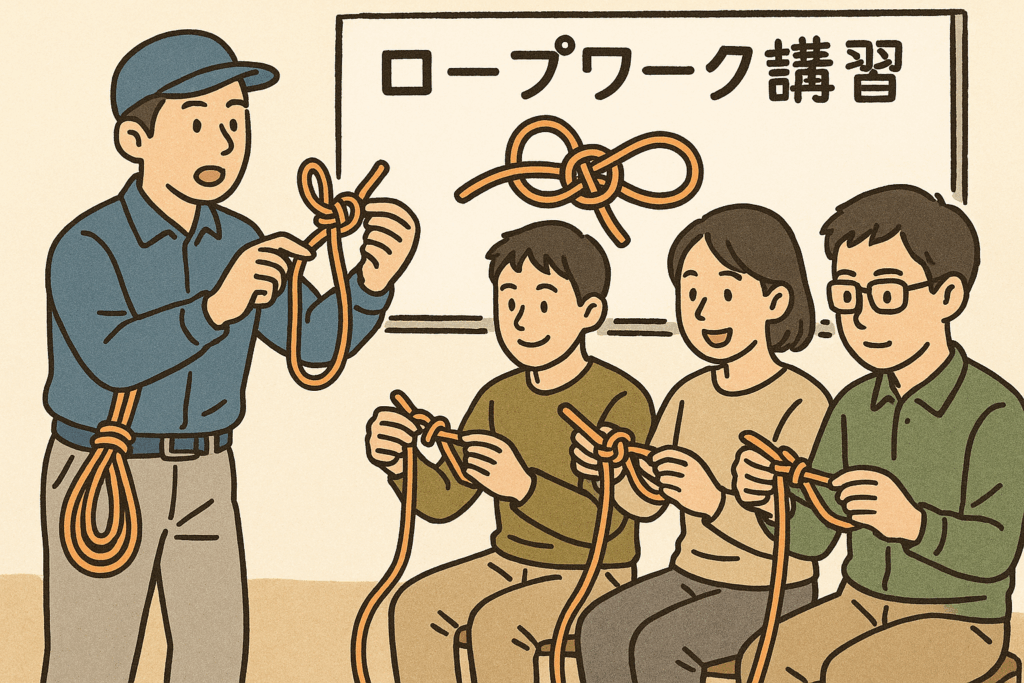
毎年同じ避難訓練。でも、本当にそれで命を守れるでしょうか?
形だけの訓練は「安心のふり」にすぎず、いざという時には役立ちません。
🏫 学校・地域に残る“昭和型”訓練
- 整列してから避難
「まずは運動場に整列」…その間に倒壊や火災の危険が迫ります。 - スリッパ行進
上履きのまま校庭へ。瓦礫やガラス片の中では危険。靴や防護具が必須です。 - 机の下で一斉待機
潜るだけで終わり。揺れの後にどう動くかを学んでいません。 - サイレン一斉退避
決まった時間に避難開始。本番に“予告”はありません。 - 校庭で点呼して終了
「無事でした」で終わるが、実際は避難所生活・情報伝達が待っています。
🏢 事業所・地域の“形だけ”訓練
- 消火器ごっこ
消火器を握るだけ。火源確認・避難誘導・通報が伴わなければ意味がありません。 - 避難経路が一つ
毎回同じ階段。実際には煙や炎で通れない可能性があります。 - 炊き出し=カレー訓練
楽しいだけで終わり。実際は水不足・燃料不足・アレルギー対応が課題です。 - テント設営なし
避難所訓練なのに仕切りや段ボールベッドを使わない。プライバシーや寒さ対策を無視しています。
🚨 共通する問題点
- シナリオが単純すぎる(地震→避難→点呼で終了)。
- 「やらされ感」が強く、実際の役立ち感がない。
- 豪雨・停電・長期避難など、多様な災害を想定していない。
📊 避難訓練の比較表
| 項目 | 形骸化した昭和的訓練(無駄な避難訓練) | 現実に即した改善された訓練 |
|---|---|---|
| 行動開始 | 教師の「机の下に入りなさい」という指示を待ってから行動 | 子ども自身が揺れを感じたら即座に自発的に行動する |
| 避難先 | 無条件で校庭集合。集合が目的化 | 耐震性がある校舎では教室内待機も選択肢。津波・火災など実際の危険に応じて判断 |
| 余震対応 | 本震だけを想定し、余震は無視 | 余震を想定し、繰り返しの揺れに対応する訓練を実施 |
| 停電・通信 | 放送設備や電気が常に使える前提 | 停電で放送が使えない状況を想定。声掛け・自主判断で避難 |
| 天候条件 | 雨天時は順延、快晴時だけ実施 | 大雨や荒天でも実施し、現実の悪条件下での対応を体験 |
| けが人対応 | 「けが人なし」で全員無事想定 | けが人を想定した「けが人封筒訓練」や応急対応を組み込む |
| 評価基準 | 集合までの時間を重視 | 「揺れから命を守る行動」「判断力・対応力」を重視 |
| 心理面 | 不安やパニックは想定外 | 実際に不安や過呼吸が出ることも前提にして訓練 |
| 教育効果 | 指示待ち型で主体性が育たない | 子どもが自ら考え、判断して行動できる力を育成 |
🪢 ロープワークは必要か?
形骸化した訓練の典型が「ロープワーク講習」です。
- 使う機会が少ない
実際に必要なのは避難誘導や安否確認など。ロープを結ぶ場面はほとんどありません。 - すぐ忘れる
反復が必要で、一度習っても数か月で忘れる人が大半。 - 道具で代用できる
結束バンド・カラビナ・ワンタッチテントで十分。 - 子どもには不要
まず学ぶべきは「逃げ方」「判断」「情報の受け取り方」。 - 訓練をむしばむ
恒例行事化すると、本当に必要な訓練(夜間避難や要支援者対応)が後回しになります。
📝 結論
ロープワークは消防団や救助隊には有用ですが、一般市民向けの訓練としては効果が薄く、優先度は低いのです。
✅ これから必要な訓練
- 避難所開設を想定した訓練(トイレ・食料・プライバシーをどう確保するか)
- 夜間・雨天・停電下での避難訓練
- 高齢者や要支援者を含めた避難訓練
📝 まとめ
本当に命を守る訓練とは「形」ではなく「現実」に即したものです。
みなさんの地域や学校の訓練は、いざという時に役立ちますか?
👉 今こそ“時代遅れの避難訓練”を見直し、命を守るための 本物の訓練 へ変えていきましょう。
参考資料
実践的な防災教育の手引き 文部科学省
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/jissenbousaisyougakukou.pdf