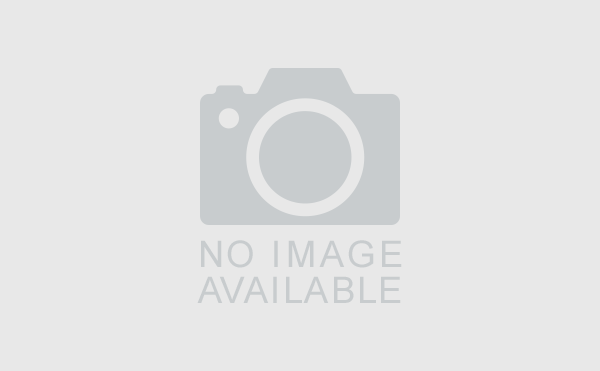🌾 地域災害予報士 構想(案)
―― 防災士が地域の未来を見守る、新しい地域防災のかたち ――
はじめに
私たち 日本防災士ネットワーク は、地域の防災力を次の段階へ進めるために、
「地域災害予報士」 という新たな構想を検討しています。
これは、単なる「地域限定の災害予測」ではありません。
地域の防災対策に主体的に関わる防災士が中心となり、
地域の観測・伝承・科学データを結びつけることで、
“住民がつくる防災”を実現する取り組みです。
1. 観測所の減少と、地域防災士の新しい使命
国の観測網は効率化の影響で縮小が進み、
局地的な災害――突発的な豪雨や斜面崩壊など――の予測精度は低下しています。
一方で、地域に根ざした防災士は、
日々の空、川、山の変化を感覚的に捉え、
住民と行政をつなぐ立場にあります。
「夕焼けが赤すぎると翌日は雨」「山がかすむと大雨」――
こうした地域の経験知を科学的視点で整理し、
“失われた観測点”を地域の力で取り戻す。
それが地域災害予報士の使命です。
2. 郷土史・伝承が示す「生きた防災データ」
各地には「いなむらの火」のように、
災害を生き延びた知恵が 伝承・地名・碑文 として残っています。
郷土史家や地域研究者が掘り起こしてきたこうした記録は、
科学データの薄い時代の“民間観測網”とも言えます。
- 「○○川の水が濁ると必ず洪水になる」
- 「この地区は昔“流田”と呼ばれていた(実は氾濫原)」」
これらの伝承には、**地域住民の観測と経験が蓄積された“生きたデータ”**が眠っています。
防災士がこれを体系的に整理し、現代防災に生かすことが求められています。
3. 科学と地域記憶をつなぐ「地域災害予報士」
この構想の中心にいるのは、防災士です。
AI・衛星・観測所などの科学的データだけでは補えない部分を、
地域の防災士が観測者・解釈者・実践者として補完します。
すなわち「地域災害予報士」は、
- 科学の“観測不足”を地域の記憶で補い、
- 防災士として現場の危険箇所や課題を見つけ、
- 行政・住民と協働して具体的な防災対策に結びつける。
この三位一体の役割を担う存在です。
4. 物語としての提案ストーリー
昔、村人全員が観測所だった。
空を見上げ、川の流れを読み、山の匂いを感じて暮らしていた。
やがて近代化が進み、観測は科学に委ねられ、
住民の“勘”は忘れられた。
しかし今、観測所は減り、地域予測の限界が見えてきた。
だからこそ――
「科学 × 郷土史 × 市民観測」 の力をもう一度結び直し、
地域の防災士が“現代の稲むらの火”となる時代が来ています。
5. 防災士講座との統合構想
本構想では、既存の防災士講座をベースにしながら、
次の要素を統合していきます。
- 地域の地形・地名・伝承を読み解く「郷土史講座」
- 日常観測を共有する「地域観測レポート」
- 科学的知識と照らし合わせる「市民観測データ解析」
- 最終的に防災計画・マイハザードマップ作成へとつなげる演習
これにより、防災士が**「講座で学んで終わり」ではなく、
地域で実践し、政策や防災会議に提言する立場**を確立することを目指します。
6. 日本防災士ネットワークの挑戦
この「地域災害予報士」構想は、
日本防災士ネットワークが中心となり事業化を進める計画です。
観測所が減る時代にこそ、
地域の防災士が“生きた観測所”となり、
科学と郷土の知恵をつなぐ役割を果たす。
それは、防災士という資格の新しい進化でもあり、
地域の防災行政と市民を結ぶ社会的モデルでもあります。
👉 「未来を守るために、あなたが現代の稲むらの火になる。」
✍️ おわりに
地域災害予報士の構想は、単なる“新しい肩書”ではありません。
それは、防災士が地域に根ざし、科学と記憶を橋渡しするための新しい実践の形です。
この挑戦に共感いただける防災士・自治体・研究者の皆さんとともに、
新しい地域防災のモデルを築いていきたいと考えています。